

↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み
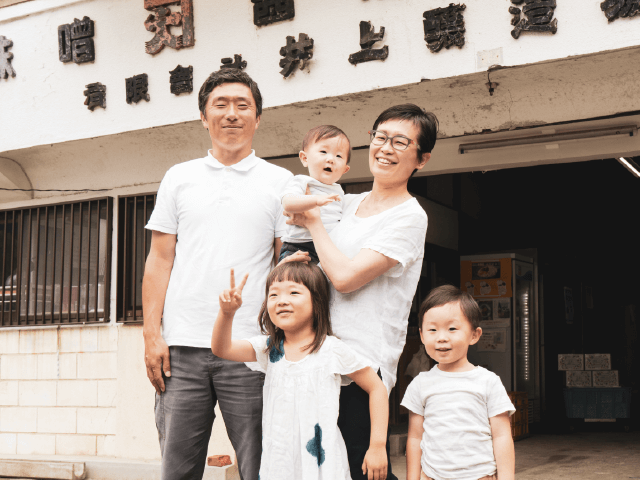

↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み
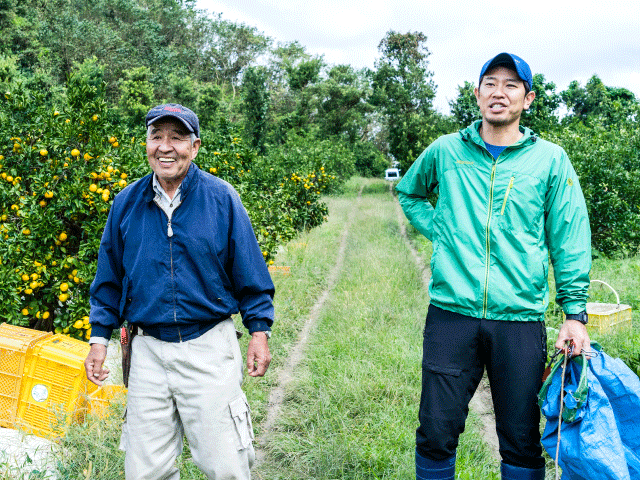

↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み
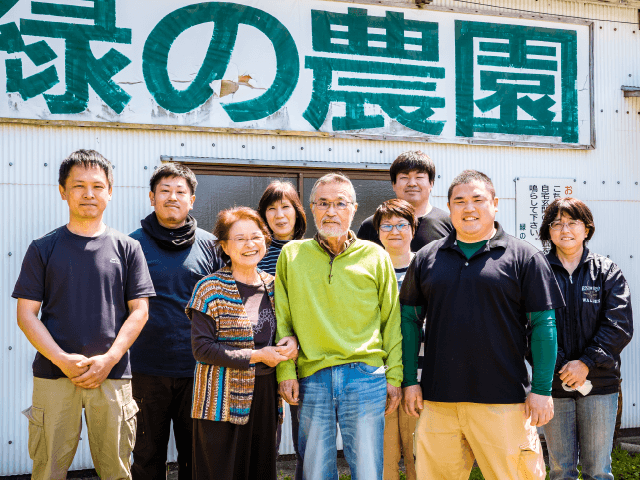

↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み

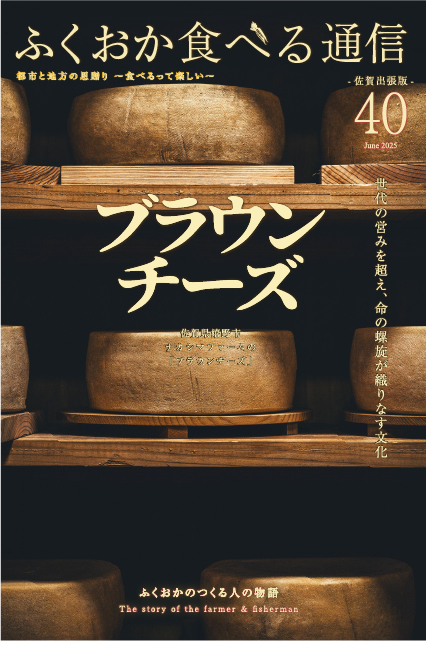
↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み


↑クリックで立ち読み

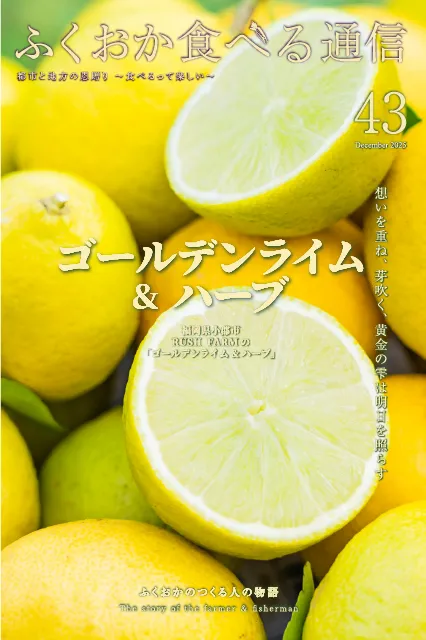
↑クリックで立ち読み